Speakers
スピーカー
※ 登壇者は予定であり、変更する可能性がございます。
あらかじめご了承ください
スピーカー
※ 登壇者は予定であり、変更する可能性がございます。
あらかじめご了承ください

1991年、千葉県生まれ。幼少期をアメリカ・ピッツバーグで過ごし、4歳から医師を目指す。東京医科歯科大学医学部卒業後、総合診療科医。予防医学の普及と医療アクセシビリティ向上を目指し、2018年6月に株式会社ウェルネスを創業。データを活用した包括的予防医療を提供するパーソナルドクターサービスなどを展開し、800名以上の経営者や著名人の健康をサポートしている。著書に『医師が教える経営者のための戦略的健康法』『医師が教える内臓疲労回復』。

小児科医、現在は勤務医として、集中治療/救急部門でこども達の診療に携わる。臨床を継続しながら。2017年から「Health 2.0」の運営に参画。今後もヘルステック新規事業にアンテナを張りながら、ヘルスケア領域の課題解決のためを日々向き合っていきたい。東京女子医科大学医学部卒業。

株式会社LYNXS代表取締役。日本のIT黎明期から活躍する女性現役プログラマーで、株式会社ゼストを創業し36年間代表取締役を務め、訪問看護・介護のスケジュール自動化SaaS「ZEST」により現場の生産性向上を実現。2019年Healthtech
Summitピッチでは敗者復活戦から最優秀賞・Aflac賞をダブル受賞。
訪問現場だけでは不十分と感じ、在宅医療・介護全体の連携課題を解決するためLYNXSを設立。異なるツールを使う多職種が自然に協力し合える非同期連携基盤を提供し、人手不足解消とケアの質向上、現場の持続可能性の両立に挑む。制度・地域を越えて連携可能な社会インフラを目指している。

University of California Berkeley Haas卒。ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)でデジタル戦略に従事後、韓国発B2CベンチャーVCNCの日本立ち上げに参画し、SaaSのEventHubを共同創業。BCG Digital Venturesでは日米中でヘルスケアを含む新規事業の立ち上げを複数推進し、プロダクト部門責任者に就任。2021年にALYを共同創業。

日本最大のSMOにて新規事業開発、臨床研究・食品試験をサポートするCRO、SMO子会社の代表取締役を務めた後、東証一部上場企業の取締役に就任。その後、治験の被験者募集を行う企業にてSMO事業の立上げ及びグローバル部門の責任者としてアジアネットワークの構築に携わる。同社にて、日本初となるDCTのインフラを構築し、ナーシング治験のローンチを手掛けた後、2022年に当社に参画、執行役員に就任するとともに、株式会社DCT Japanを立ち上げ、同社取締役に就任
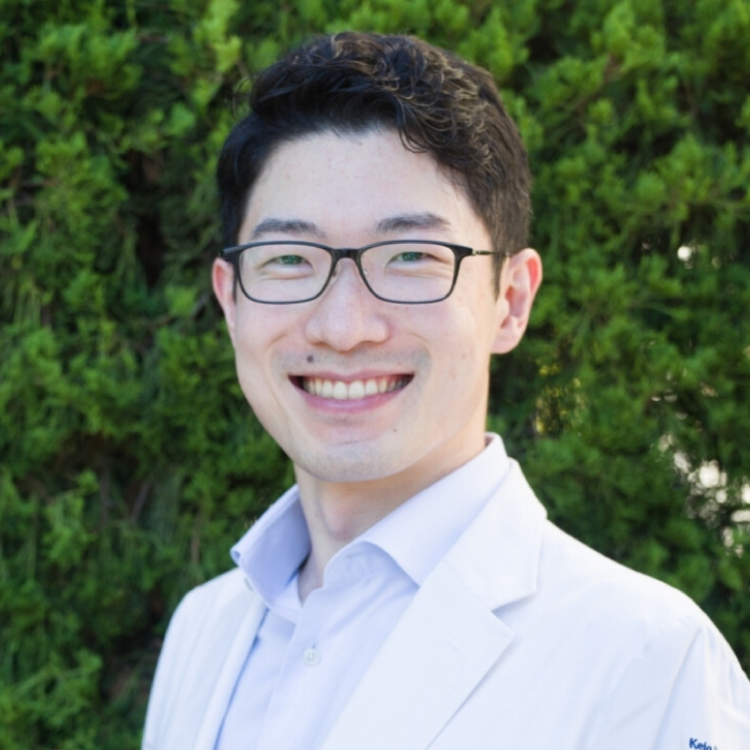
2人に1人が生涯でがんに罹患する時代、がん医療は年々進歩し複雑になってきています。がんと診断されても動揺しない社会を目指して、腫瘍内科医、そしてデータサイエンティストとして、臨床および研究の両面からがん患者さんの歩む道を照らすことを目指しています。

欧州および米国の外資系製薬会社を経て2022年12月よりインスメッド合同会社。新製品の事業化準備を始めとして、多くのコマーシャル関連部門の機能化に従事。承認薬のマーケティングオペレーションから、新薬の上市を見据えたStrategic Marketingに至るまで、医療用医薬品の事業モデル開発に精通。

京都大学大学院情報学研究科修了。
2002年経済産業省入省。その後、資源エネルギー政策やバイオ技術政策などに携わり、原子力発電所事故収束対応室長、ガス市場整備室長を経て、2025年7月に現職。

日本電信電話株式会社へ入社し、NTTコミュニケーションズ(株)にてISP・映像サービスのマーケティングを担当した後、日本電信電話(株)へ異動し、経営企画部門を経験。
2012年より(株)NTTドコモに在籍し、dポイントクラブ会員へのマーケティング戦略および顧客エンゲージメント強化に従事。
2023年7月よりヘルスケアアプリとオンライン薬局の運営を通じて、PHRサービスやオンライン診療・服薬指導の普及およびヘルスケア・メディカル領域におけるDX を推進。

1982年、中国・河南省生まれ。東京工業大学卒。シリアルアントレプレナー(連続起業家)。
東京大学修士在学中に、東大発ベンチャーpopInを創業し、2015年にBaiduと経営統合。世界初の照明一体型3in1プロジェクター「popIn Aladdin」や大ヒットゲーム「スイカゲーム」などを開発。
2021年、issin株式会社を創業。国内初のお風呂上がりに乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット」をリリース。2025年、装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる指輪型デバイス「Smart Recovery
Ring」を発売。2025年11月、著書「道具としてのアイデア」を出版。
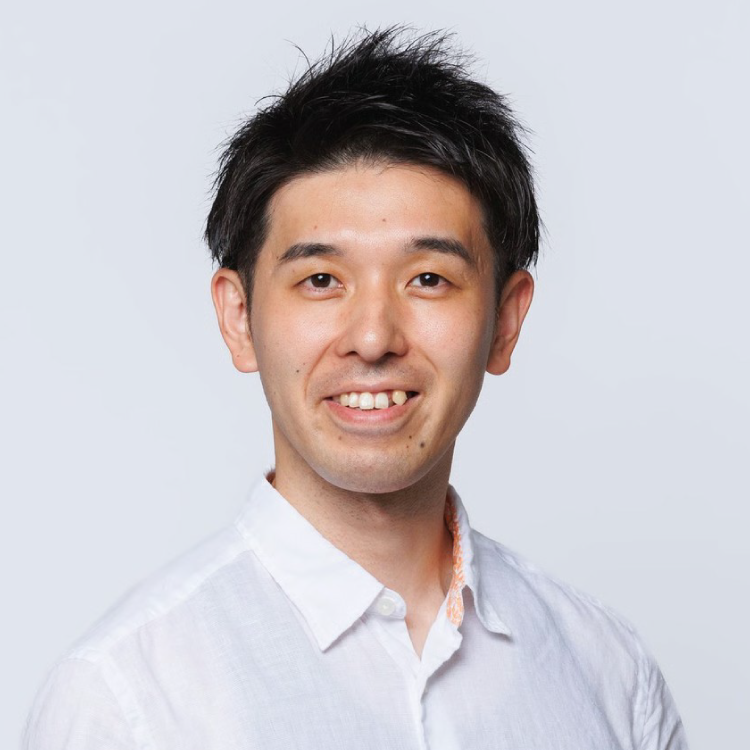
楽天でUI/UXやPMの仕事を5年、ウォンテッドリーで新規事業のBizDevの責任者を3年務め、2019年、独立。楽天時代は楽天PointClubの立ち上げPMなどを中心に、10個以上のサービス、アプリの立ち上げとBizDevを経験(TizenやWindow10アプリも経験)
Wantedly 時代は、Wantedly Peopleの立ち上げから成長までをリード。CMのディレクションや、大企業のアライアンスもリード。
大学の友人の林とともに、「難しい社会課題の解決にお金が流れない」ことに対する問題意識から、ヘンリー を創業。

2009年、東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻にて学位取得(工学博士)。同年、中外製薬に入社し、新規モダリティである“中分子”を使った創薬技術起ち上げに従事。その後、創薬プロジェクトリーダーや機能マネージャーとして様々な中分子創薬プロジェクトに、主にHit創出(=薬のタネを見つける事)の観点から関与。2023年、モダリティ基盤研究部長、研究本部DXリーダーに就任し、中分子創薬やデジタル技術を中心とした創薬プラットフォーム技術開発を担っている。

2018年東京大学医学部卒。日赤医療センターや東大病院等で臨床業務に従事し、皮膚科専門医、医学博士号を取得後、2025年4月よりGoogle合同会社に入職し、Clinical Specialistとしてヘルスケアやライフサイエンスのプロジェクトに従事。

国内最大規模の診療データベースを保有するメディカル・データ・ビジョン株式会社に2007年入社。病院経営支援システムの企画・販売を経て、診療データ利活用事業責任者に就任。2018年より同社取締役。現在は、営業・企画部門の統括とアライアンス戦略を担当。医療ビッグデータ利活用を推進する上で大事にしていることは、「病院・患者メリットの最大化」。
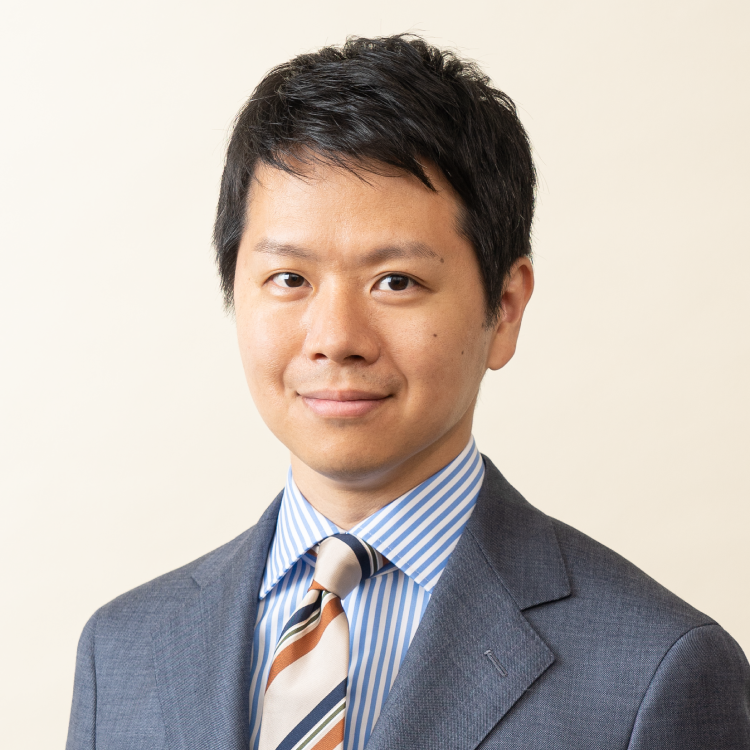
名古屋大学理学部卒業後、外資系製薬企業にて営業・マーケティング・組織文化開発に従事。京都芸術大学でのデザイン思考の学びを活かし、医療ITスタートアップにて、国立循環器病研究センターを中心とした研究プロジェクトに企業代表として参加。医師の意思決定を支援する生成AIの社会実装を目指し、株式会社Cubecを創業。
芸術修士・学際デザイン研究領域・京都芸術大学大学院
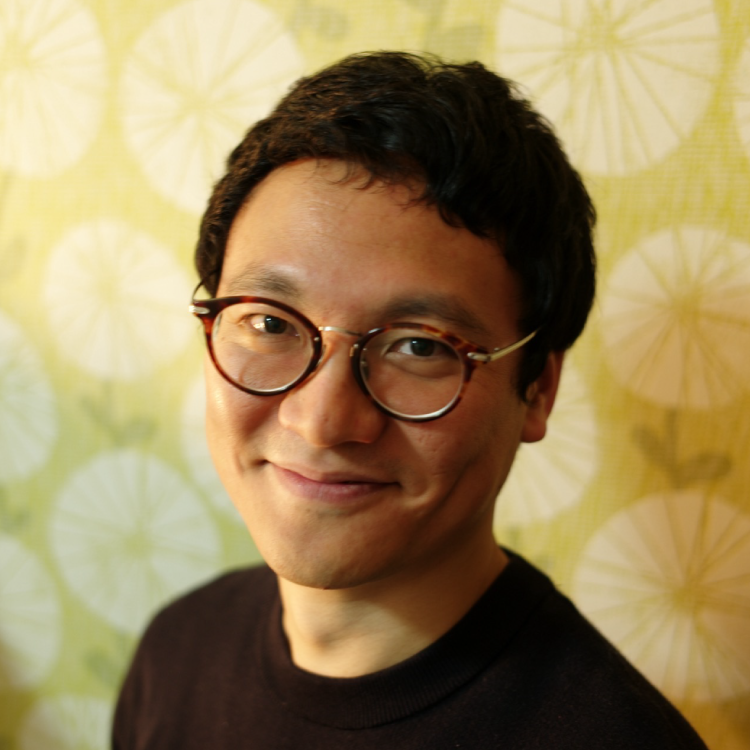
2010年に富士通で法務としてキャリアを開始、ワシントンDCのシンクタンク(CSIS)での客員研究員、バンクーバーで新会社設立と新規事業開発に従事。2020年に、国内外でのM&A、資本業務提携・JV、ベンチャー投資、新規事業開発を手掛ける新組織、Strategic Growth & Investments(SG&I)を立ち上げ、室長、Capital Alliances Leadを歴任。2024年4月1日から現職。

1999年に信州大学医学部を卒業し、東京女子医科大学病院循環器内科学に入局。
循環器内科医として勤務する傍ら、2004年12月にメドピア株式会社(旧、株式会社メディカル・オブリージュ)を設立。
2007年8月に医師専用コミュニティサイト「MedPeer(旧、Next
Doctors)」を開設し、現在15万人の医師(国内医師の約4割)が参加するプラットフォームへと成長させる。2014年に東証マザーズ、2020年に東証一部(現:東証プライム)に上場。
2015年より、ヘルステックにおける世界最大規模のグローバルカンファレンス「HIMSS & Health 2.0」を日本に誘致して主催。 現在も医療の最前線に立つ、現役医師兼経営者。
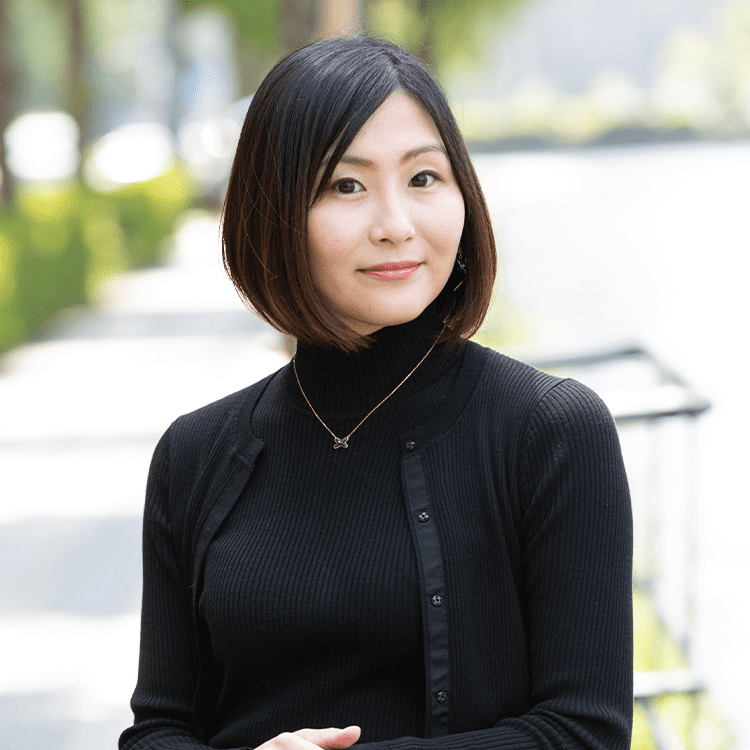
形成外科、在宅訪問診療医。医療法人向生會理事長として高齢者の褥瘡管理を中心に100名以上の高齢者ケアに携わる。
臨床を継続する傍ら、ビジネスと医療をつなぐ翻訳家、ヘルステックプロモーターとして活動。2017年よりヘルステック領域のグローバルカンファレンス(メドピア・日本経済新聞主催)に統括ディレクターとして参画。現在はHealthtech
Summitとイベント名を変更してヘルスケア領域のイノベーションのハブとなっている。
また、自身が代表を務めるスタートアップでは、医師の専門性をビジネスサイドに活用するためのプラットフォーム「Medivisor」を提供。企業の新規事業開発支援や学術機関との共同研究の推進、国内外のベンチャー支援など、ヘルスケア事業の縁の下の力持ちを目指して事業開発をしている。
早稲田大学法学部卒、岡山大学医学部卒

1999年、慶應義塾大学法学部卒業後、2000年に福神株式会社(現アルフレッサ株式会社)入社。
2016年、子会社エス・エム・ディ株式会社の代表取締役に就任し、希少疾病治療薬の流通スキームを構築。
2020年、アルフレッサ株式会社の代表取締役社長に就任。
医薬品の安定供給を使命とし、患者に寄り添う革新的なソリューションを通じて医療現場の効率化支援と質の向上に取り組む。

マシュー・ホルト氏は、The Health Care Blog や、 HIMSSに売却されたHealth 2.0
カンファレンスをインドゥ・スバイヤ史とともに創始したことで知られている。現在ホルト氏は、ヘルステックベンチャーのためのSMACK ヘルスアドバイザリーサービスを運営し、THCBGang チャット/ポッドキャストをThe Health
Care Blogというウエブサイトで主催している。
ホルト氏は、30年以上もの間、ヘルスケアやデジタルヘルス分野でアナリストや戦略家としてキャリアを積んできた。特に、未来研究に特化したInstitute For The Future (IFTF: 未来研究所) や調査会社 (Harris
Poll)等で、ヘルスケアを多面的そして詳細にわたり研究した草分け的な存在であり、世界各国にて基調講演を開いてきた。人脈も広い。
Matthew Holt is best known as the founder of The Health Care Blog and (with Indu Subaiya) the Health 2.0 conferences,
sold to HIMSS a while back. Now he runs the SMACK.health Advisory service for health tech startups, and hosts the
THCBGang chat show/podcast on The Health Care Blog.
During his career he has spent more 30 years (!) in health care and digital health as a generalist forecaster and
strategist, having worked for renowned forecasting (IFTF) and polling (Harris) organizations, conducted several
groundbreaking in-depth studies about many aspects of health care and delivered several keynote addresses all over the
world. He knows a few people too.

病院にスマートフォンを導入し、地域における積極的なICT活用による働き方改革を推進、ひとの「いきるを支える」医療提供を目指すとともに、医療分野におけるDX推進に尽力する。2024年10月より日本病院DX推進協会を発足、代表理事を務める。

株式会社Preferred Networksテックリード。博士(理学)。2021年東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。同年4月より現職。深層学習を用いた医用画像のデータ解析案件や医療ドメイン向けの大規模言語モデルの研究開発に従事。日本語医療LLMのLlama3-Preferred-MedSwallow-70BおよびPreferred-MedLLM-Qwen-72Bの開発をリード。

外資系コンサルティングファームでキャリアをスタートし、新規事業開発や企業変革プロジェクトに従事。その後、ヘルスケアスタートアップにて患者向けサービスの事業開発を担い、現場の声に根ざした価値創出に取り組む。
患者さんの治療体験をより良いものにしたい――その想いを原点にJMDCへ参画し、現在は製薬企業向け新規ソリューションの開発をリード。データとテクノロジーを活用し、ヘルスケア領域に新たな選択肢を生み出すことを目指している。

2014年埼玉医科大学卒業後、亀田総合病院に入職。安房地域医療センター救急科・総合診療科を経て、亀田総合病院救命救急科に所属。同院にて救急専門医、在宅医療専門医取得後、三重県志摩市民病院にて副院長、病院長代行を担う。2024年に株式会社FLOCALを設立。医療を通して持続可能な地域作りを行うために、全国の病院や自治体に対して、プロジェクトマネージャーとして、救急・総合診療・在宅などGeneralistとしての診療・部門運営支援や病院経営改善、地域に必要な病院作りなどを行なう。2025年総務省病院経営アドバイザー。

大学院修了後、コーポレイト ディレクションを経て、2009年にDeNAに入社、HR本部長、モバイルゲーム事業本部長、経営企画本部長を歴任。
2017年にシニフィアン株式会社を設立。2019年、総額200億円のグロースファンド「THE FUND」を設立し、急成長企業の継続グロースを支援する投資を行なう。
ラクスル、ツクルバ gumiの社外取締役を務めるほか、株式報酬イノベーションによってスタートアップの成長を加速させるNstock株式会社のエグゼクティブ・アドバイザーも務める。

大手製薬企業での勤務経験のあと、2003年にNTTデータに入社。製薬業界向けの新規事業開発に参画後、臨床開発/流通/営業/PMSなど広範な製薬プロセス変革等をプロジェクトマネージャー/ディレクターとして推進。2021年11月より、次世代医療基盤法認定データベース事業(千年カルテ)に従事中。

1999年に京都大学医学部を卒業後、7年間消化器外科医としての臨床経験を積み、2006年より国立がん研究センター中央病院でJCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)の運営、管理にあたる。2015年より国立がん研究センター中央病院で医師主導治験の支援部門を立ち上げ、日本最大規模の支援機能を有する組織を構築。2020年より厚生労働省、AMEDの支援のもと、アジア臨床試験ネットワーク事業(ATLAS project)をプロジェクトリーダーとして率いるとともに、GCP renovationや生成AIに関する厚生労働科研研究班、DCTに関するAMED研究班で研究代表者を務める。

製薬企業のMRからキャリアをスタートさせ、事業会社でリアルワールドデータを活用したエビデンス創出やサービス開発の経験を積んだ後に、現職である株式会社ディー・エヌ・エーに入社。DeSCヘルスケア社へ出向し、データ利活用事業の立ち上げを行った。健康・医療分野のリアルワールドデータを活用した研究を支援し、エビデンス創出を促進するだけでなく、生活者接点のあるアプリケーションや保健事業を通じた健康寿命の延伸と医療費適正化の課題解決に取り組んでいる。

1989年日本商事株式会社(現:アルフレッサ株式会社)入社。関西地域における営業の要として、大阪南支店、阪神第二支店長、大阪北営業部長を務めた後、調剤薬局統括部長を経て、2018年 執行役員に就任。医薬営業本部 調剤薬局統括部長、北関東・甲信越営業本部長を務める。2020年4月に常務執行役員、翌年4月に取締役に就任し、営業部門の管掌役員として、医薬営業統括本部長就任。2023年6月よりアルフレッサホールディングス株式会社グループ医療卸事業統括部グループ医薬卸営業推進担当を兼務。取締役 常務執行役員として新規事業部門であるソリューション&イノベーション事業部長を務める。2024年4月より現職。

2016年TMI総合法律事務所入所。2023年ジョージタウン大学ロースクール修了(National and Global Health Law LL.M/ Food & Drug Law Certificate)。2024年ニューヨーク州弁護士資格取得。2025年厚生労働省医療系ベンチャー・トータルサポート事業(MEDISO)サポーター就任。日米の医薬品・医療機器等規制及びヘルスケアコンプライアンスに精通しており、日頃から日系企業の米国進出・事業展開をサポートしている。医療AI案件の経験も豊富。主な著書に『米国FDA医薬品・医療機器規制入門』(商事法務、2024年9月)。セミナー講師実績多数。

眼科専門医、認定産業医。臨床を継続する傍ら、ライフサイエンス・ヘルスケア・ウェルネス領域のアドバイザーやコンサルティングを中心に、国内外の医療系スタートアップや研究シーズの実用化支援等、レギュラトリーサイエンスとビジネス、医療現場と産業の架け橋となることを目指して活動する。前職ではPMDAの審査官として、精神神経系、麻酔、感覚器領域の医薬品や医療機器、再生医療等製品の開発相談や承認申請審査を多数担当した。京都大学経済学部、岡山大学医学部卒業。
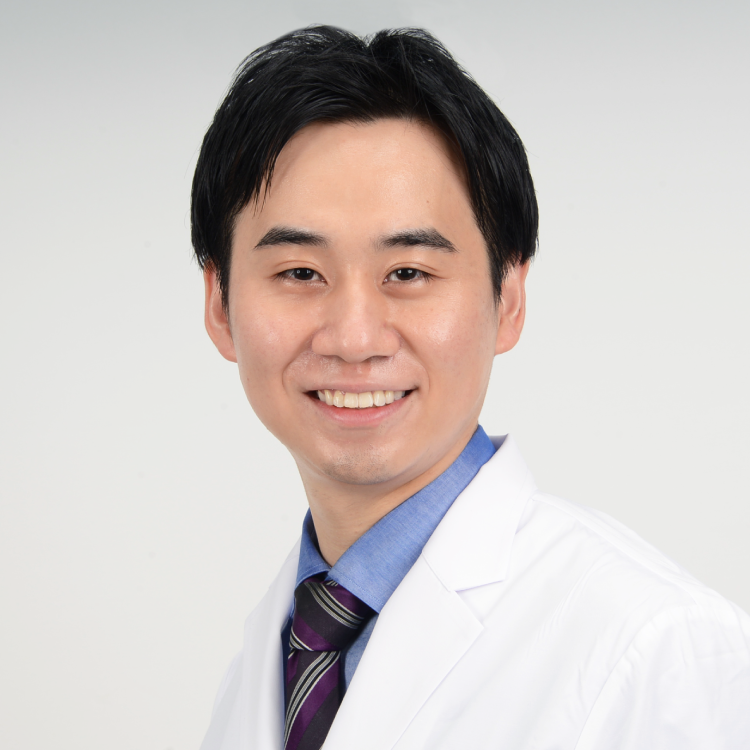
医師。2017年3月筑波大学医学群医学類卒業。2019年4月より順天堂大学医学部放射線治療学講座に所属し、がんの放射線治療に従事。2024年10月から聖マリアンナ医科大学放射線治療科助教を兼務。2020年6月、エンジニアやデータサイエンティストと株式会社TenGenを共同創業し、医療のIT・DX推進に取り組む。専門は脳腫瘍・頭頸部腫瘍・皮膚腫瘍・悪性リンパ腫の高精度放射線治療、ならびに婦人科腫瘍の小線源治療。

Eighty-Eighty Therapeutics株式会社の創業者兼社長であり、ボストンに拠点を置くブティック系の投資銀行Locust Walkのアジア代表も務める。世界中の医薬品のライセンス活動や、M&Aのアドバイザーを務める傍ら、自身でもバイオテック企業を運営し、複数社の取締役にも従事している。現職以前は、サンバイオ株式会社の執行役員として、日本およびアジアにおける再生医療の拡大に貢献し、参天製薬では、アジアのマネージングディレクターおよび参天製薬中国の副社長を務め、ASEAN地域および中国における事業立ち上げと運営を統括した。エーザイ株式会社やアッヴィ社では、日本における販売およびアジア地域での事業開発活動を主導した。同志社大学で物理化学工学の学位を取得し、シンガポール国立大学でMBAを取得。

2005年治験被験者募集専門会社のクリニカルトライアル創業メンバーとして参画
2009年同グループにて製薬企業向け治験広告専門クロエ創業メンバー
(現エムスリーG、3H社)両社の取締役を経て
“テクノロジーの力で一人でも多くの患者さんへ新たな選択肢を”をミッションに掲げ、日本の新薬開発を活性化し、ドラッグラグ・ロスを無くすため、治験をより効率化するプラットフォームの開発・運用を行う株式会社Buzzreachを2017年に設立

2021年聖マリアンナ医科大学入学。大学向けアプリ、医療機器、ヘルスケア機器などの設計、開発を手掛ける。2021年慶應健康医療ベンチャー大賞準優勝。
2022年に医学部と理工学部生が中心となるメンバーで株式会社Pleap(現株式会社medimo)を共同創業、代表取締役に就任。 2023年にAIにより医師のカルテ記載業務の負担を軽減するプロダクト「medimo」のβ版をリリース。

2015年より、医療・ヘルスケア領域のスタートアップ、総合商社グループにて新規事業開発責任者として、医療・介護・ヘルスケア×ITに関わる事業を推進。その後、静岡社会健康医学大学院大学 准教授(現任)として、ヘルスケア関連の産学連携・オープンイノベーションやビジネスモデル分析などの教育・研究に従事。2024年より、株式会社メドレー オープンイノベーション パートナーに就任(現任)。ヘルスケア特化のエンジェル投資家として42社に出資。Ph.D(京都大学、Public Health)、MBA

2020年4月㈱ユカリア(旧社名:キャピタルメディカ)に参画、2021年3月取締役就任、2024年3月より現職。「医療・介護のあるべき姿」を追求し、病院の経営支援、高齢者施設運営、高齢者施設紹介、医療DX推進、医療ビッグデータ利活用といった事業を通して社会課題の解決に取り組む。「ヘルスケアの産業化」を掲げ、社会的インパクトを創出すべく奮闘中。
東京大学大学院修了後、ゴールドマン・サックス証券、モルガン・スタンレー証券、メリルリンチ日本証券で要職を歴任した後、㈱ドームにて常務取締役を務める傍ら、2017年に東大アメフト部監督、2018年に筑波大学客員教授に就任。好きな食べ物はカレーとハンバーグ。

山形県出身。大学院時代はスーパーコンピュータを利用したシミュレーションで宇宙物理の研究に従事。株式会社ディー・エヌ・エーにエンジニアとして入社。その後、シンガポールのスタートアップにて多国籍のエンジニアチームをリード。2016年に株式会社Elixを創業。理学博士。

内科医。高齢者向けの訪問診療『東京むさしのクリニック』院長。2011年に「医学教育という専門領域から、日本と世界の明るい未来を創造する」という理念の元、株式会社リーフェホールディングスを設立。将来の医師を育てる医学生向けの個別指導塾『医学生道場』の運営や、自らが『ドクターハッシー(内科医 橋本将吉)』というYouTubeで健康教育を行う。2022年9月に、健康や医学を医師から学ぶ事のできるサービス『ヘルスケアアカデミー』をリリース。また、2023年11月には現役の医師目線で日々を健康に暮らすためのアイテムを扱うライフスタイルブランド「ハシモトマサヨシ」を立ち上げ、商品を展開している。

・早稲田大学先進理工学研究科博士課程卒。ロボット工学を専攻。
・文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」としても活動。
・トビタテ!留学JAPAN4期(オーストリアのams社にて1年間インターンシップ参加)
・在学中にWASEDA-EDGEプログラムを通して起業に興味をもち、2018年博士課程に入学と同時に株式会社Genicsを設立、ロボット技術で人々の生活を豊かにすることを目指す。
・2019年1月にアメリカラスベガスで開かれたCES 2019で次世代型全自動歯ブラシを発表。
・ロボットの研究で培った知識で子供へのロボットを活用した教育にも従事。

プロサッカー選手を目指して大学までサッカー部に所属し全国大会を経験。睡眠グッズEC企業やマットレスの販売を経て、睡眠指導者として独立。アスリートやビジネスパーソンの睡眠指導を確立。その中で"睡眠負債という課題は社会・組織から変革していかないと解決できない"という社会課題に気づき、企業や組織が測定しやすい日中の覚醒度に着目。科学的に確立された指標から睡眠負債を解消することに特化したサービスNemieluを考案。その後、スリープテック企業を経て、ネミエルを設立。睡眠改善インストラクター/睡眠健康指導士/睡眠環境・寝具指導士などの資格保有。日本睡眠学会/日本睡眠環境学会正会員。
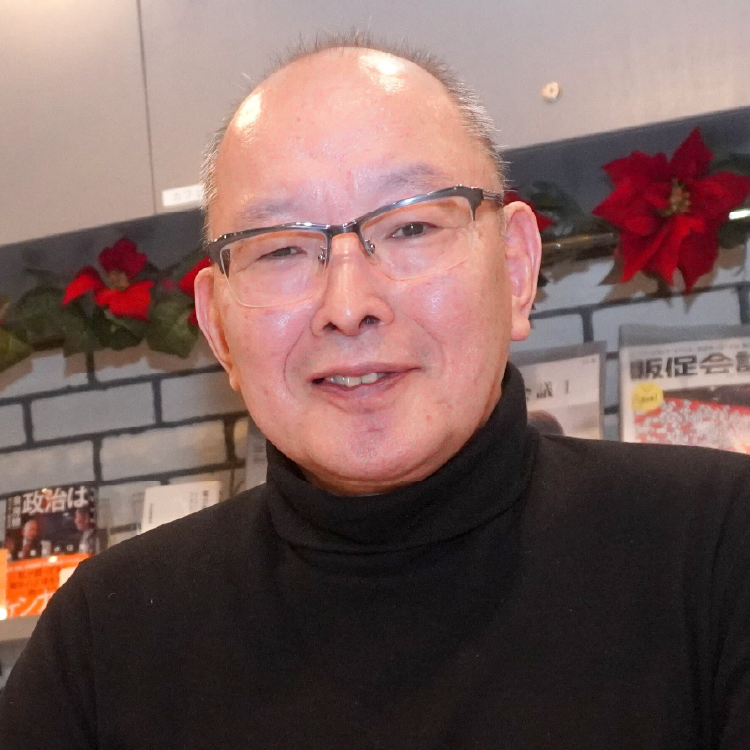
1956年生まれ。動作解析AIの開発中、独居の実母が転倒し発見が遅れた経験から、既存見守りシステムの限界を痛感。「本当に役立つセンシングとは何か」を探求し、起業を決意。健康寿命の延伸こそが本人・家族・社会にとって最大の幸福であるとの信念のもと、インタビューやアンケートで現場の声を徹底的に収集。見守りサービスが普及しない真因を分析し、その不満と不安を解消する非装着・壁貼型センサーを開発。誰もが自宅で健康に暮らし続けることができる社会の実現をめざしている。

作業療法士として、医療機関、在宅医療での臨床経験、経営企画、地域連携等の新規事業構築への関与を経て、2024年5月に株式会社ジョシュを共同創業。2025年に医療介護の情報連携効率化システム「連携ジョシュ」をリリース。
日本臨床作業療法学会理事、運転と作業療法学会理事

京都大学大学院修了後、新卒でトヨタ自動車にて先進安全技術の開発を推進。その後AI系スタートアップ2社を経験。異物検知システムの開発や手術用AIシステムなど医療機器開発全般を主導していた。
2022年3月に株式会社アークスを創業、代表取締役に就任。
精子評価AIシステムや卵子評価AIシステム、顕微授精の自動化システムの開発を主軸に事業を展開している。
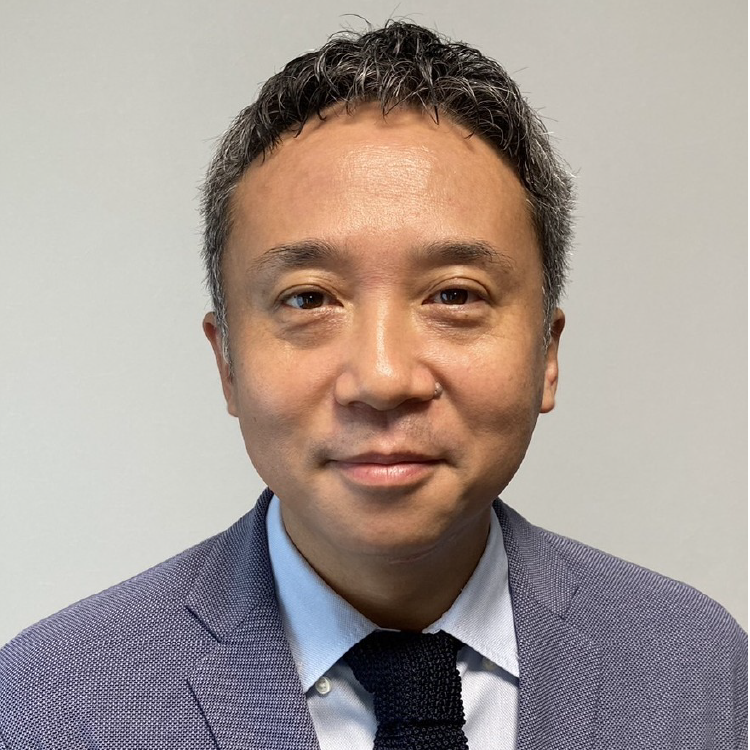
民間企業にて営業、開発、品質管理、製造の各業務に従事。現職では産学連携の実務担当として、特許戦略を踏まえた出願・契約業務から、マーケティングやライセンス交渉までを一貫して担当。企業の新規事業立案にも関与し、大学発シーズ18件の事業化・製品化に成功。2023年にEgret・Labを創業し、高純度・高回収なエクソソーム精製技術を基盤に受託精製サービスを開始。今後は大量精製ツールの製造・販売を展開し、創薬分野への応用を見据えて、薬効の安定したエクソソーム製剤の品質管理・評価体制を構築し、CDMO構想の実現を目指す。
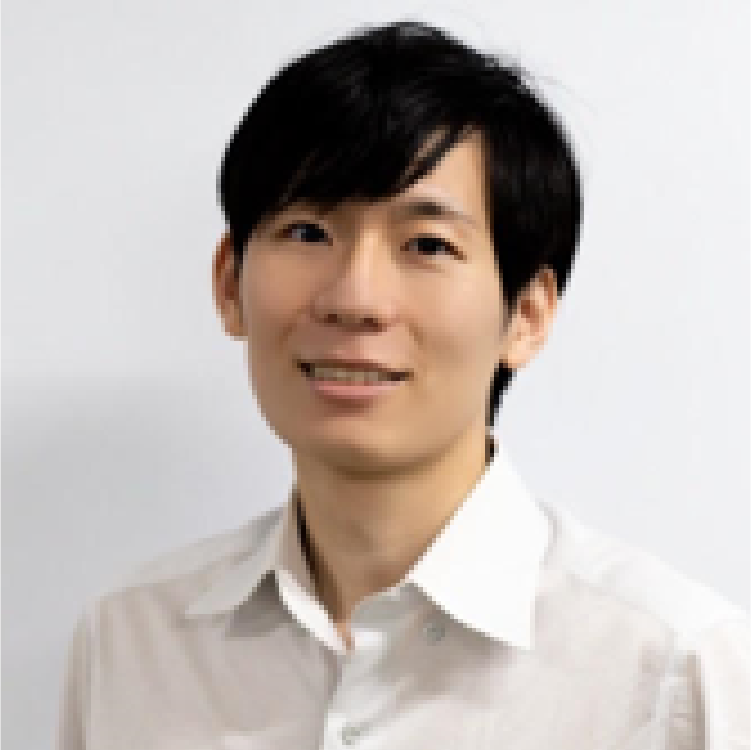
日本トップレベルの医療AI研究者(主著論文被引用数:約2,000回)。16歳で東京大学に合格。博士(情報理工学)。医用画像データ不足を解消する研究を国内外で10年以上続けており、この問題を本質的に解決すべく、日本の多様かつ高品質な医用画像データセットを流通するカリスト株式会社を創業。大阪大学 招へい准教授・長崎大学 特任准教授・日本デジタルパソロジー研究会 理事を兼任。YouTube発信(登録者数約7万人)をきっかけに「日曜日の初耳学」「激レアさんを連れてきた。」など各種メディアに出演。

株式会社SOIK 創業者・代表取締役
東京大学農学部卒。JICAにてアフリカ各地の開発援助に従事し、コンゴ民主共和国では現地事業の統括を担当。社会的インパクトを創出するソリューションが生まれない現状に危機感を抱き、起業を決意。スイスIMDでMBA取得後、沖縄にて開発途上国向け医療機器開発企業のCOOを経て、2019年に株式会社SOIKを創業。同年、コンゴ民主共和国に現地法人を設立。
母子保健DXプラットフォーム「SPAQ」を通じて、アフリカ農村部の妊産婦・新生児死亡率低減に取り組む。医療アクセスが限られた地域にも革新的なソリューションで質の高い医療提供を目指す。

1999年に社会調査研究所(現:株式会社インテージ)に入社。システム開発事業、リサーチ事業などを経験後、2012年4月 マーケティング支援(ヘルスケア)事業の中核を担うアンテリオ(現:株式会社インテージヘルスケア)にグループ内異動。2017年4月に株式会社インテージヘルスケア 経営企画部長、その後2022年7月より同社取締役に就任。取締役として事業開発部門を担当し、ヘルスケア事業のシナジー創出やアライアンスなどを推進。2023年7月より現職。

1986年、山之内製薬株式会社(現・アステラス製薬株式会社)に入社。2010年に買収した米国子会社のCEOに就任。2012年にAstellas Pharma Europe Ltd.に出向し、欧州・中東・アフリカ事業の経営戦略担当Senior Vice Presidentを務める。アステラス製薬帰任後は、事業開発部長、経営企画部長、経営戦略担当役員などの要職を歴任。2019年6月から代表取締役副社長経営戦略担当。2023年4月に代表取締役社長CEOに就任。

2021年10月よりSalesforceにてキャリアをスタート。「世界の医療をより良くする」をミッションに、医療・保険業界担当のソリューションエンジニアとして活動。Salesforceの最新のテクノロジーを駆使し、患者様、医療従事者様の体験向上と組織のビジネス課題を解決するためのソリューションを提案。最新の業界トレンドと技術知見を組み合わせ、お客様のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進を伴走支援。

北里大学を1987 年に卒業後、外資系製薬企業に入社。営業本部に所属し、医薬情報担当者(MR)として活動。この経験を踏まえ、1992 年から製薬業界向け日刊紙の記者として厚生労働省、製薬業界、医学・医療界の取材に従事。キャップ、デスク、編集長を経て、2008年12月にエルゼビア・ジャパン株式会社に移籍、Monthly ミクスの編集長に就任。2017年7月に株式会社ミクスに、ミクス事業が承継され、同社の代表取締役兼ミクス編集長として現在に至る。

1993年 京都大学薬学部卒業、同大学院薬学研究科にて博士(薬学)取得。
同大学院医学研究科・特定教授を経て2016年 京都大学大学院医学研究科
ビッグデータ医科学分野・教授、現在に至る。
理化学研究所計算科学研究センター・部門長、一般社団法人ライフインテリジェンスコンソーシアム・代表理事、ならびに日本学術会議・幹事を併任。
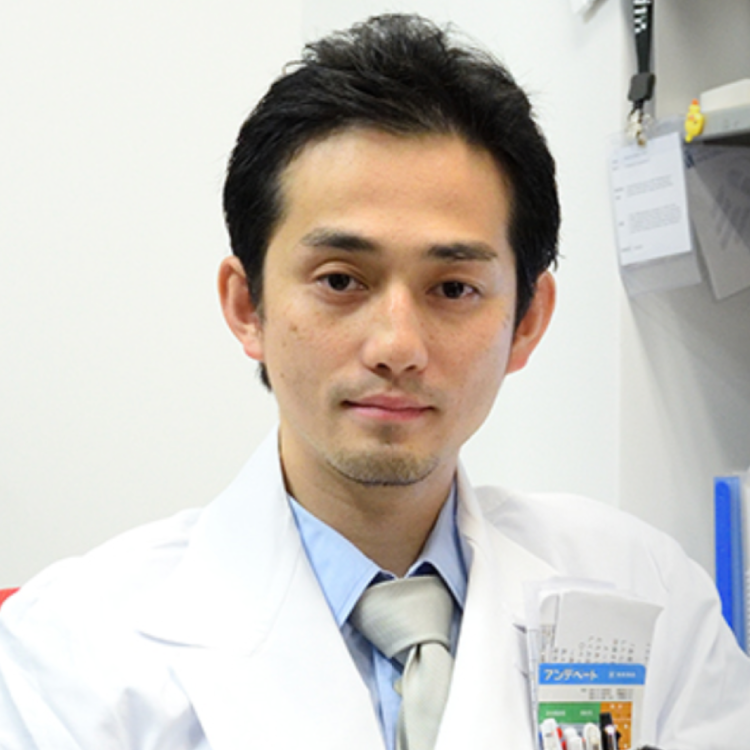
2008年に東海大学医学部を卒業後、順天堂大学総合診療科で臨床・教育・研究に携わり、アイルランド国立小児研究センターでの研究留学を経験しました。新型コロナウイルスのパンデミック時には、厚生労働省で感染症危機管理に従事し、国の対策現場で医療現場との連携や調整を担当しました。その後、欧州疾病予防管理センターで、国際的視点からの公衆衛生と危機管理を学びました。また、東南アジアの医学教育支援を目的に NPO法人アプサラ を設立し、現地医学生との交流や教育プログラムの構築に取り組んできました。現在は順天堂大学医学部准教授として、生成AIと模擬患者を活用した新しい医学教育の創出に注力しています。

システムインテグレーターでシステムエンジニアとして幅広い企業のネットワークやサーバーインフラの構築・保守に従事。その後、医療業界へ転身し、病院向けの画像診断システムの導入・運用保守を担当。さらに地域医療連携システムや医療クラウド・AI画像診断システムのプリセールス等に携わる。2022年1月より現職。Account SEとしてB2C企業やヘルスケア・ライフサイエンス企業を中心にDX推進を支援。

武田薬品工業でMRとしてキャリアをスタート。その後、マーケティング部に異動し、前立腺がん・乳がん領域を中心に担当。同領域プロダクトのブランドリードを経て、セールス&マーケティングのヘッドを務める。2022年11月よりSalesforceにて、ヘルスケア・ライフサイエンス業界のマーケティングを担当。早稲田大学大学院でMBAを取得し、デジタルヘルスに関する論文を執筆。

1980年3月に浜松医科大学を卒業。1988年に埼玉県大宮市(現さいたま市)に松本皮膚科形成外科医院を開設。1996年に大宮医師会理事、2006年に同医師会副会長、2010年に埼玉県医師会理事、2011年に同医師会常任理事、2014年に大宮医師会会長を経て、2016年に日本医師会常任理事に就任。2017年から2021年まで厚生労働省「中央社会保険医療協議会」の委員を務め、2022年6月より第21代日本医師会会長に就任。

聖路加国際大学(旧:聖路加看護大学)大学院博士前期課程修了、看護師・保健師・助産師。
順天堂大学医学部付属順天堂医院に7年勤務するが、仕事と育児の両立ができなくなり退職。忙しい割には患者との時間が少なく、個人の努力だけでは大好きな仕事を継続することができない環境に違和感を持つ。ITで看護師がより看護に集中できる環境を作るためにジーズアカデミーへ入学、GlobalGeekAuditionにて当時初めて、審査員賞とオーディエンス賞を同時受賞。医療系ベンチャー企業にてエンジニアインターンを経て、現メディカルギーク(株)を設立。現在は聖路加国際大学の臨時助教として、看護・助産学生の育成にも励んでいる。

アステラス製薬等の大手製薬企業で、研究開発・経営企画の両部門に従事。研究開発では、創薬テーマの創出から開発(米国特許取得実績あり)までを主導。経営企画では、日米欧のグローバル市場分析に基づき、中長期製品戦略を立案し、開発品・販売品のライセンス交渉を成功に導いた。その後、再生医療のバイオベンチャー企業では、プロジェクト推進部長・社長室長・創薬技術研究センター長を歴任。全社ポートフォリオ最適化、NPV評価による事業性判断、経営方針策定、上市計画を統括し、組織を牽引。2024年7月、Veritas In Silicoに入社。創薬から事業化までの一貫した経験と戦略的視点で同社に貢献する。

2005年司法試験合格、2006年東京大学法学部卒業。2013年ジョージタウン大学ローセンター(LL.M.)修了、同年ニューヨーク州司法試験合格。外資系法律事務所でのM&A、コーポレート支援業務を経て、現職。ベンチャー企業支援及びヘルスケア業界を含む企業の法務・コンプラインスを専門とし、現在はスタートアップ企業の社外監査役等も務める。2021年6月~2023年3月東京都「Blockbuster TOKYO」メンター。厚生労働省医療系ベンチャー・トータルサポート事業(MEDISO)サポーター、経済産業省Healthcare Innovation Hub(InnoHub)アドバイザーも務める。

Dr. Chan Yoon は整形外科医・研究者・起業家であり、筋骨格系ケアのデジタル革新を牽引しています。現在、AIを活用した遠隔リハビリおよびデジタル治療を提供する企業、EverEx のCEOを務め、同社のソリューションは韓国、シンガポール、米国の100以上の医療機関で採用されています。以前はソウルブミン病院臨床研究センター長兼主任研究員、Beplus Lab最高医療責任者を歴任。膝関節外科、運動器バイオメカニクス、デジタルヘルス分野で30本以上の国際論文を発表。AIと行動科学を融合した疼痛治療ソフト「MORA Cure」の主要研究者としてMFDS認可を取得。ソウル大学医学部でMD・MSを取得し、同大学院で整形外科PhD課程在籍中。KAIST生物学士。多数の政府表彰を受賞。

1999年厚生労働省入省、医政局、保険局、健康局等を経て、2025年7月から現職。

専門分野は医療データ活用と行動変容による疾病予防。
2004年、米国カーネギーメロン大学に企業派遣されMBA取得。
2004年から5年間、マッキンゼーのヘルスケア部門に所属したのち、2009年から5年間、IQVIA JAPANにてレセプトデータ活用の事業立ち上げを担当。
2014年~2018年まで株式会社JMDCにて代表取締役社長として医療データ活用や保健事業支援に注力。
2019年よりスギ薬局にてデジタルヘルスを担当し、2024年のスギウェルネス株式会社(スギHD100%子会社)設立とともに代表取締役社長に就任。

兵庫県姫路市出身。東京大学農学部大学院にて生態学を研究。
早期に社会へインパクトを出すため将来的な起業を決意。ITコンサルティングベンチャーにて、プログラミングや業務コンサルティングに2年半従事。モバイル・インターネットキャピタル(株)にてベンチャー投資や経営支援を6年半実行。電子カルテベンチャーへの投資を通じ、医療・病院と関わりを持つ。
2017年、メダップを創業。病院の経営/事務の高度化・効率化を目指す。

2001年に愛媛大学医学部を卒業後、同大学放射線科に入局。2011年にはボストンのMGHに留学。2020年より愛媛大学大学院医学系研究科 放射線医学講座 教授。
循環器画像診断と人工知能(AI)解析技術を専門とし、心臓CTによる虚血性心疾患の精密評価や、医用画像ビッグデータを活用したAI基盤構築をリードしている。愛媛県民の画像と診断レポートのクラウド化を推進し、地域医療の質と持続性を高める取り組みを展開。
医学部長補佐としては「愛媛大学医学部支援基金」の活性化を通じて寄附文化を育み、地域との共創を推進。病院長補佐としては医療の質と働き方改革を両立させる体制づくりに尽力している。

昭和63年東京大学入学、平成4年法学部卒業、厚生省に入省。平成8年老人診療報酬改定、平成20年・28年の診療報酬改定に携わったほか、平成16年の初期臨床研修制度の制度設計等に参画。平成23年から桑名市役所で勤務し、市立病院と民間病院の再編統合に携わった。このほか、ジェトロNYセンターでは製薬産業の米国進出支援を、医政局経済課では製薬・医療機器産業政策を担当。また、老健局振興課では、高齢者の在宅介護政策を担当するなど、医療や介護分野を中心に30年余りのキャリアを積む。医学・医療分野の研究費助成を行うAMED(エーメド)の理事を経たのち、令和6年7月よりデジタル庁審議官。令和7年7月より現職。

Daniel Szpilman is working for Takeda Pharmaceuticals with international experiences in Europe, the Middle East, the US, and Japan. He has 10 years of experience across multiple commercial functions such as Public Affairs, Market Access, Pricing, Sales, Marketing, Corporate Development, and Finance, focusing on a variety of therapeutic areas such as Oncology, Neurosciences, or Immunology. He is currently working for the Takeda Headquarters in Tokyo in Global Finance. Daniel is a lawyer by training, and holds a PhD in Patent Law and Bioethics from the University of Zurich and the ETH Zurich.

金沢大学医学部卒業後、沖縄県で研修し米島で離島医療に従事。持続可能な医療への疑問を機に慶応義塾大学MBA取得。2011年、在学中に心療内科・総合内科医をしながらiCAREを創業。卒後、iCARE立ち上げとともに病院再建・黒字化に貢献。2016年、法人向けクラウド健康管理システム「Carely」をローンチ。現在はSaaSと専門人材による支援を融合し、健康データの蓄積・活用を通じて、企業が健康課題を戦略的かつ計画的に解決できる仕組みを提供。2025年10月オムロングループへ参画。2018年厚生労働省の検討会委員を務める。著書『産業医はじめの一歩』(羊土社、2019年)。プライベートでは四児の父。

帝京大学医学部卒業後、医師として整形外科・救急科に従事後、2016年にファストドクター株式会社を創業し代表取締役に就任。「生活者の不安と医療者の負担をなくす」をミッションに掲げ、一億人がアクセスできるプライマリケアプラットフォームを提供。ForbesJAPAN日本の起業家ランキング2023第1位受賞、経済産業省JHeC2021優秀賞、ICCKYOTO2019優勝、The10thAsiaEldercareInnovationAwards最優秀賞、日本スタートアップ大賞2025厚生労働大臣賞受賞。日本整形外科学会専門医/認定脊椎脊髄病医、東京都医師会在宅医療委員会委員、帝京大学医学部非常勤講師。

1996年 群馬大学医学部卒業。2005年 大阪大学医学部医学系研究科生態統合医学(救急医学)博士課程、2006年 京都大学大学院医学研究科・臨床研究者養成コース修了。 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 予防医療学分野 教授/PHR普及推進協議会代表理事。専門は臨床疫学、蘇生科学、健康科学。産官学民連携によるPHRサービスの質向上、普及に力をいれている。将来の夢はログビルダー、釣り人。

Philipp Hoelzerは、現在シーメンスヘルスケアのアジア太平洋地域において、アドバンスト・セラピー事業本部のイノベーション責任者を務めています。
同地域の著名な臨床パートナーと連携し、低侵襲手術、インターベンショナル・ラジオロジー(IVR)、インターベンショナル・カーディオロジーをはじめとする分野において、術中ガイダンスのイノベーションを推進しています。
現職以前は、シーメンスヘルスケアのDiagnostic Imaging事業本部において、さまざまな国や部門で多様な職務に従事していました。
電気工学のドイツディプローム学位、および物理学の博士号を取得しています。

2008年インテージグループに入社、CRO事業の臨床開発、安全性情報、製造販売後調査のビジネス戦略立案、実行を担当。2019年株式会社インテージヘルスケア設立以降は事業開発、経営企画部門の責任者を歴任、複数の全社プロジェクトを推進し、現在プロモーション事業の事業開発を担当。プロモーション/コミュニケーション領域において株式会社NTTドコモの顧客基盤の活用および株式会社協和企画の医療系広告代理店の知見を活かしたデータドリブンなソリューションの開発を進めている。

2000年4月に福神株式会社(現 アルフレッサ)に入社。営業として東京都内の開業医を9年半担当した後、都内大学病院を8年半担当。2018年10月、病院支店長に昇格。2021年度はこれまで蓄積した開業医および病院での営業ノウハウを活用し、東京営業本部推進グループ長として「新たな営業モデル構築」の活性化に従事。2022年4月、本社ソリューション部新設のタイミングで当部部長に就任。ステークホルダーが抱える課題を起点としたソリューション営業の支援、企画立案、開発に従事。2024年4月、更なるソリューション推進をMissionとするS&I事業部イノベーションアーキテクト部の新設と共に着任。現職に至る。

2009年横浜市立大学医学部医学科卒。横浜労災病院初期研修医を経て2011年より横浜市立大学大学院医学教育学・消化器内科学、2015年3月に医学博士。大学院在学中の2014年10月に株式会社メディカルノートを共同創業、2024年12月に代表取締役を退任。2025年6月より株式会社GENOVA取締役執行役員に就任。横浜市立大学共創イノベーションセンター特任准教授。大阪大学招聘准教授。京都大学客員研究員。日本医療機能評価機構EBM普及推進事業運営委員。日本デジタル医学会理事、将来構想委員長。2008年北京頭脳オリンピック”WMSG”チェス日本代表。

1980年生まれ、東京と神奈川で3つの一般皮膚科を経営する 皮膚科専門医。
2014年 溝の口駅前皮膚科開院、
2019年 自由が丘ファミリー皮ふ科開院、2020年 二子玉川ファミリー皮ふ科開院。
著者は3冊。
経営セミナーが好きで、自身の開催する開業医エキスパート交流会を毎月渋谷で行っている。

医療機器メーカーにてキャリアを始動。一貫して医療・ヘルスケア領域の発展に尽力する。
ヘルスケア特化型コンサルティングファームでは、最高執行責任者として病院経営改善、産学連携、異業種企業の新規参入支援など多岐にわたる課題解決で多くの実績を積み上げた。
その後、学会向けSaaS「Menergia」を提供する株式会社メネルジアの代表取締役社長として医療DXの最前線を牽引。現在はメドピア株式会社の医療機関向け事業責任者として、病院予約システム「やくばと」など、現場の課題を解決する仕組み作りに注力している。医療現場と産業界を繋ぐイノベーションの架け橋として、未来の医療を創造すべく、挑戦を続けている。
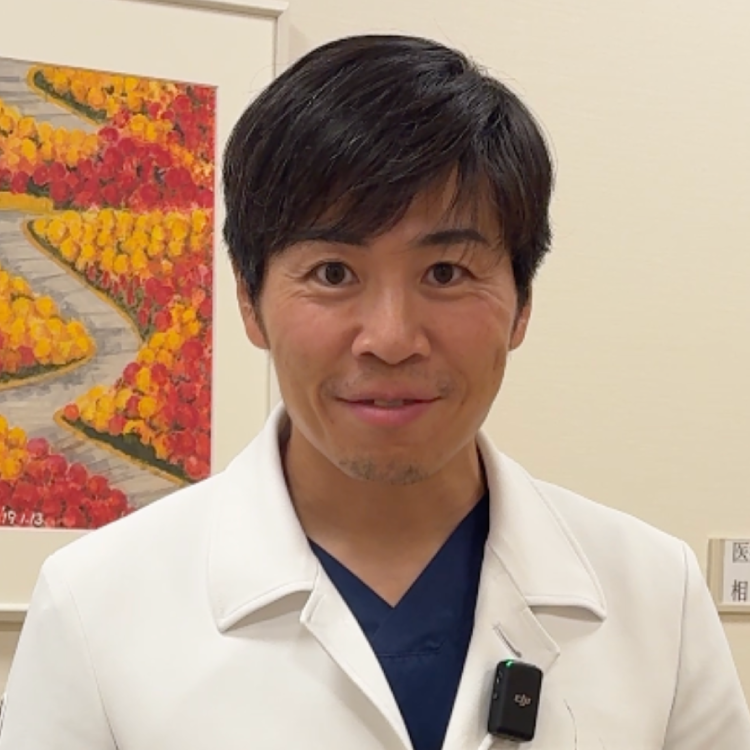
1981年東京都生まれ。高校卒業後、家業の靴屋を継ぐつもりでいたが、19歳の夏に友人の死をきっかけに医師になることを志す。
2009年北里大学医学部卒業、2011年慶應義塾大学病院整形外科学教室に入局。
医師と患者のマッチング環境に疑問を感じ、2019年に東京の足立区に自身が医師として信頼できる整形外科のみを集めた病院とクリニック当日開院。

Levi Shapiro is a global DeepTech connector. Based in Tokyo, active in the US and Israel, he is the co-Founder of Kizna
Growth Capital. Previously, he worked in several venture funds, including Gemini, Veritas and Life Science Vision.
During this period, he also created and operates mHealth Israel (12,000+ members), the largest and most active community
for healthtech entrepreneurs in Israel. Until recently, he was based in Israel and was Faculty in the BioMed MBA program
at Hebrew University.
Mr. Shapiro launched his career in international roles at multinational corporations including Toyota and IBM. He is
fluent in Japanese and Italian and held leadership roles in Europe and Asia.
As an entrepreneur, Mr. Shapiro founded four startups, funded many and currently sits on the boards of several DeepTech
companies. He is a graduate of Tulane, Cornell and MIT.

1987年東京都生まれ。高校時代に同級生を自殺で亡くしたことをきっかけに精神科医を志す。
2012年東邦大学医学部卒業後、同大学の精神神経科に入局。精神科単科病院やクリニックなど多様な医療現場で研鑽を積み、2022年に「メンタルドクタークリニック」を開業。
臨床の傍らYouTuberとしても活動し、精神科やメンタルに関わる情報発信を続けている。総フォロワーは15万人を超え、これまで4冊の著書を執筆。

医師、医学博士、産業医。
2014年に厚生労働省へ入省。2017年にメドレーへ参画し、オンライン診療に関するGovernment
Relationsやアカデミアとの連携を推進した。2020年からはソフトバンクにて、DTx領域の投資検討および海外企業とのJV設立を担当。2021年に株式会社ヘッジホッグ・メドテックを設立し、2023年より東京科学大学の客員准教授も務める。
ヘッジホッグ・メドテックは、2025年11月にベルシステム24から「頭痛ーる」事業を承継し、頭痛に悩む人へのデジタル支援をさらに推進している。

日本医科大学医学部卒。2005年にカンボジアで小学校を建設し、その体験記は映画化された。2014年に新生児医療支援のNPOを設立し、カンボジアやタンザニアで活動。現在はエレコム株式会社ヘルスケア事業部の執行役員として医療×テクノロジーの社会実装を推進。MediBuddyとの協業や新生児蘇生シミュレーター「Saving baby」の普及に取り組み、医療の届きにくい地域への貢献を目指す。
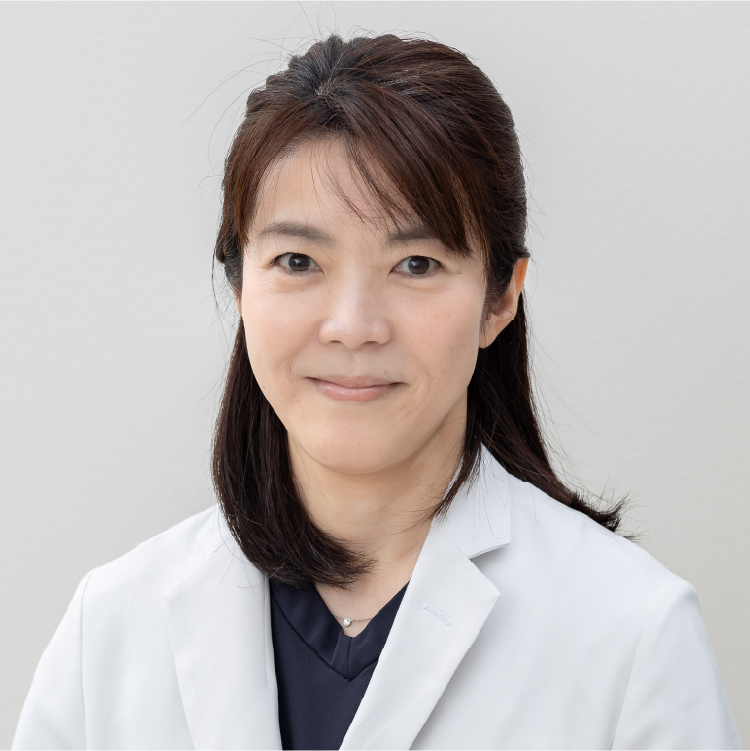
京都大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科にて診療も行いつつ、代謝や栄養に関する臨床研究や企業との共同研究、プログラム医療機器の開発をしています。

Richard is a Research Lead at Innovation Lab, one of ASTELLAS PHARMA R&D divisions, in Japan. He is currently leading
the development of early-stage R&D programs from ideation to early clinical evaluation with a strong focus on delivering
therapeutic solutions that can change the life of patients.
Prior to this, he has spent about 15 years leading scientific and cross-functional teams in several European biotech
companies developing innovative products for regenerative medicine, diabetes and autism spectral disorder, in
particular.
Richard has a PhD in Chemistry from North Carolina State University and an executive MBA from EMLyon Business School.
He is the co-author of 19 publications and inventor of more than 45 patent applications.

ハーバード公衆衛生大学院・同 経営大学院修了。内科・循環器科専門医を取得後、医薬品医療機器審査センター(現PMDA)、日本医師会に勤務。その後、日本人として初めて米国食品医薬局(FDA)医療機器審査官を務める。さらにBoston Scientific 米国本社Medical Director、米シリコンバレーにて医療機器スタートアップ企業へのコンサルティング業を経て、2012年 サナメディ株式会社(旧 日本医療機器開発機構)を設立。同社代表として日本初の本格的医療イノベーション・インキュベーターとして医療機器、再生医療、デジタルヘルスサービスなどの事業化に着手している。

1978年北海道生まれ、47歳
薬剤師、MBA
大学卒業後、病院薬剤師として勤務。
2004年、SMO(治験実施医療機関)で治験コーディネーターとして勤務しながらMBAを取得。(小樽商科大学、ノースウェスタン大学ケロッグスクール留学)
2016年、シミックホールディングス株式会社に入社後、医療・ヘルスケア分野の新規事業開発やM&Aに従事。
新型コロナウイルス感染症のパンデミック時には、全国の自治体から集団接種会場の設置・運営を受託。2024年、国の医療DX政策の一環として、ワクチン接種、母子健診、自治体検診のデジタル化を担う事業会社、CMIC
Trust株式会社の代表取締役社長に就任。

ソニー株式会社にアルゴリズム研究者として入社。体調不良をきっかけに「harmo(ハルモ)おくすり手帳」を開発。新規事業として全国展開し、厚労省による電子版おくすり手帳の正式認可を実現。シミックグループに事業を承継後「harmo(ハルモ)ワクチンケア」を開発。予防接種の事故を減らす活動を展開する。自治体のコロナワクチン集団接種で200万人以上の利用、外務省・厚労省による空港でのコロナワクチン接種国家プロジェクトでの利用、WHOによる世界標準のパンデミック対策ソリューションへの公式採択(日本初)等の実績を上げる。
開成高校、東京大学理学部情報科学科・同大学院卒(理学修士)

2009年4月、アルフレッサ株式会社に入社。営業職(MS)として7年半にわたり兵庫県内の医療機関を担当し、地域医療体制の強化に尽力。その後、マーケティング部門で市場分析と戦略立案を担い、東京都内では営業課長としてチームを率いる。さらに営業管理部門では全社の販売体制最適化に取り組み、生産性向上を支援。2024年10月よりソリューション&イノベーション事業部 イノベーションアーキテクト部 プロダクト・サービスグループ長に就任。医療用医薬品等の卸売事業で培った知見とネットワークを基盤に、仕組み・システム開発から新規ビジネス創出までを一気通貫で推進し、持続可能な収益モデルの構築に挑み続けている。
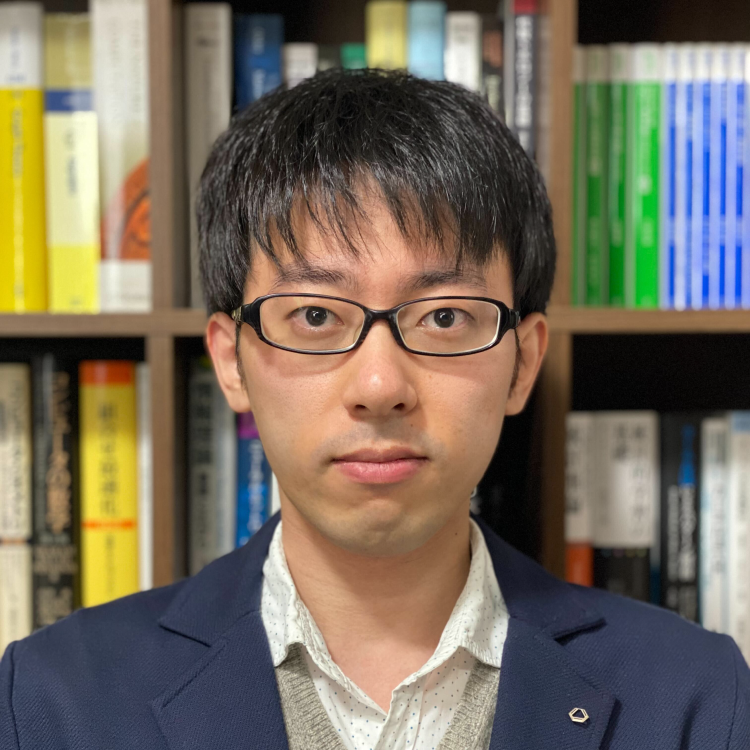
博士 (工学)。京都大学工学部情報学科で数理工学を専攻した後、修士課程から東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻でケモインフォマティクスの研究に従事。2022年4月にElix入社。書籍『詳解 マテリアルズインフォマティクス』『事例でわかる マテリアルズインフォマティクス』を共著で執筆。
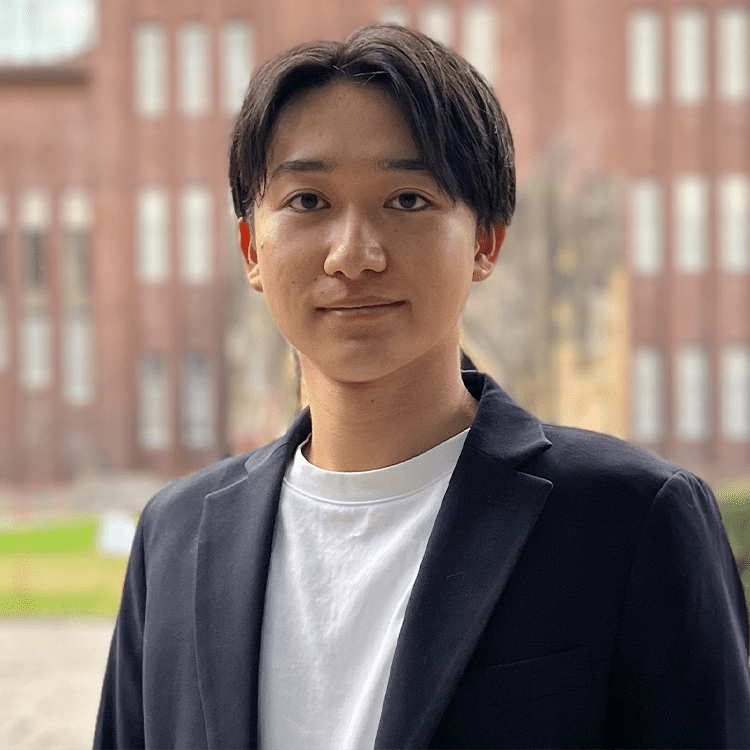
2024年に東京大学を卒業後、メドピア株式会社に入社し、プレシジョンメディシン領域での新規事業立ち上げに従事。併せて、オンコロジー領域の新規プロダクト「ClinPeer」において、肺癌・がんゲノム領域を中心としたコンテンツ制作を経て、新機能「症例検討」のPdMとして企画から開発までリード。現在はドクターリレーショングループのグループリーダーとして、癌専門医との協働を通じてClinPeerの価値創出に取り組む。

2000年に名古屋大学大学院工学研究科 有機化学分野にて博士号取得(工学)、情報処理技術者1種を取得。その後、米国Yale大学Breaker研にて博士研究員として、核酸の分子細胞生物学について研究。2003年に武田薬品工業株式会社入社、2004年より自ら提案したmRNAに対する低分子創薬プロジェクトを運営。2011年会社判断によるプロジェクト中断を受けて退社後、Dow Chemical営業部マネージャー、Catalent Pharma Solutions事業開発ディレクターを経て、産業革新機構 戦略投資ディレクターとして核酸医薬品バイオテク企業3社の取締役を務める。2016年にVeritas In Silicoを設立し、同年代表取締役に就任。